【べストは90分?】最適な筋トレ時間の長さ|長時間トレの問題点と対策

1回のトレーニングを短時間でササッと終わらせるタイプの人もいれば、毎回かなり長い時間ジムに滞在してトレーニングを続ける人もいます。
あんまり短いと筋肥大が起こりにくくなるんじゃないかと心配する一方で、長すぎるトレーニングもそれはそれで問題だと思う人もいることでしょう。
このページではトレーニングの時間はどれくらいがベストなのかについて解説します。
・長時間トレーニングの問題点
・トレーニングが長くなってしまう原因と対策
・適切なトレーニングの長さ
・長時間トレーニングのデメリットを減らす方法
1 長時間のトレーニングがよくない理由

まず始めにトレーニングが長時間に及ぶことの問題点について解説します。
ここで紹介する内容は以下の2点です。
①集中力の問題 ②筋分解の問題
1-1 集中力の低下
筋トレには集中力が非常に重要です。
対象の筋肉に負荷を載せるため、ケガ・事故の予防のためのフォーム調整に非常に多くのリソースを使います。
集中力が切れた状態でのトレーニングは効率が低下するだけでなく、シンプルに危険です。
人間の集中力は一般的に30分程度が限界といわれています。
短い人だと15分くらいとも言われていて、90分とか2時間とか集中を維持し続けることは出来ません。
集中力が低下した状態でトレーニングを続ければ効率が低下し、さらに長時間化するという負のループに入ってしまいます。
1-2 カタボリックの進行
カタボリックとは筋肉の分解のことで、筋肥大を目指すトレーニーが恐れるものだと思います。
その1つの原因となるのが長時間に及ぶトレーニングです。
筋トレのような無酸素運動は解糖系という代謝回路でエネルギーを生成し、主に糖質を消費します。
まずは血糖や筋肉内のグリコーゲンが利用されますが、トレーニング時間が長いとそれだけでは賄い切れません。
そこで次に体組織を分解してその材料を作り出そうとする糖新生が起こります。
もちろん体脂肪も分解されますが、同時に筋肉も分解されてしまうのです。
つまり筋肉を増やそうとして筋トレしながら筋肉を消費してしまうというコト。
これでは本末転倒です。
2 筋トレが長くなる原因と対策

長時間トレーニングの問題点が分かったところで、次に1回の筋トレが長時間化しやすい原因を紹介します。
「もう少しコンパクトにしたいのに長くなってしまう」という悩みを抱えてる人は、自分に当てはまることが無いか確認してみてください。
筋トレが長時間に及ぶ原因・ポイントは以下の3つです。
①分割の問題 ②負荷の問題 ③インターバルの問題
2-1 鍛えたい部位が多過ぎる
第一の理由が1回のトレーニングで鍛えたい部位が多過ぎることです。
平均的なメニューの場合、1つの部位に対して3~4種目程度で1種目当たり4~5セットくらい行います。
たった1つの部位を鍛えるだけでも20セット程度のボリュームになるということです。
大胸筋の上部~下部、三角筋のフロント~リアなど細かく分ければ、種目数・セット数はもっと増えます。
セット間のインターバルまで含めると相当な時間になるでしょう。
1回の筋トレで全身を鍛えるサーキットトレーニングや全身法が典型です。
しかし分割法でも分割があまりにザックリしてるとこの問題は起こります。
仕事やプライベートの予定などとの兼ね合いでトレーニングできる回数には限界があるでしょう。
それによって分割の数も変わりますが、なるべく4~5程度の分割にするのをオススメします。
分割を増やせない場合はセット数や種目数の調整の検討が必要です。
2-2 扱っている重量が低い
効率的に筋肥大を起こすためには、筋肉に対して適切な刺激・ストレスをかける必要があります。
「刺激=負荷の大きさ」ではありませんが、負荷の大きさが重要であることは間違いありません。
「これくらいの時間トレーニングしないと十分追い込めないんだ」という人は、自分の扱ってる重量を見直してみてください。
負荷が低すぎて十分な刺激が与えられていないために種目数やセット数を増やすことになってしまってる可能性は十分あります。
負荷が低い人の対策はシンプルに扱う重量を増やすことです。
安全面には配慮する必要がありますが、「低すぎる」というレベルなら多少上げてもさほど危険な水準にはならないでしょう。
また扱ってる重量は大きいが、負荷が対象の筋肉にかけられていないというパターンもあります。
高重量のベンチプレスを三角筋のフロントや上腕三頭筋で挙げてしまってるのが分かりやすい例です。
これではいくら負荷を上げても大胸筋には負荷は乗りません。
こういう場合は負荷を下げて大胸筋で挙げる練習をするか、ダンベルフライなどの単関節種目に切り替える対策がオススメです。
2-3 インターバル管理が甘い
最近は多くのジムでインターバル中のスマホ利用を禁止していますが、未だ一定数は要るようです。
特にトレーナー・店員さんのいない24時間ジムなどでは顕著でしょう。
他の利用者への迷惑という点でも当然ですが、トレーニング時間の長時間化という点でも問題です。
1つの部位に対して20セットやる場合、その間に19回のインターバルがあります。
1回のインターバルでロスする時間は30秒でも、それを繰り返せばトータルでは9分30秒のロスです。
3つの部位をやるならインターバルだけで30分近くムダにすることになります。
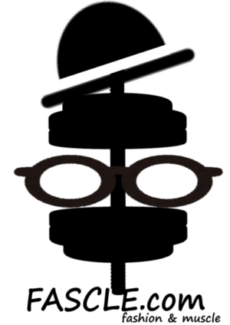
まさにチリツモ
ここでしたいのは適切なインターバルが何秒なのかという話ではありません。
具体的な時間の問題よりも、ちゃんと管理せずテキトーにセット間を過ごすことで多くの時間をムダにしてることが問題ということです。
決めたインターバルを守ってトレーニングしなければ狙った効果も得られず、ジムで垂れ流した時間の全てがムダになってしまいます。
この問題の対策は至極シンプルでタイマーを使ってインターバルを管理することです。
タイマーを使っててもスマホの依存性は強力で、なかなか気持ちを切り替えられないので、いじらないことをオススメします。
3 適切なトレーニング時間とは?


なるほど…じゃあ何分以内におさめるのがいい?
最低限のトレーニング時間の明確な基準はありません。
ただし筋肉の発達が必要だというシグナルを発するには、それなりのストレスをかける必要があります。
短いに越したことはないとはいえ、短すぎるトレーニングでは十分な効果は得られないでしょう。
自分の狙い、筋肥大に必要と考える要素をしっかり盛り込んだ上で、なるべく短縮するよう心がけるというのがベストです。
今回は長過ぎるトレーニングの問題点についての解説がメインなので、上限について触れておきましょう。
一般的には2時間を超えるトレーニングは長過ぎると言われています。
なるべく必要最低限で抑えようと考えるトレーニーは多くが45分~90分程度で設定しているようです。
ぼくも70分以内には終えるようメニューを作っています。

時間を目標にしたと言うより、日数と種目数から結果的にこうなった、が正しいかな!
4 短縮しきれないときの対策
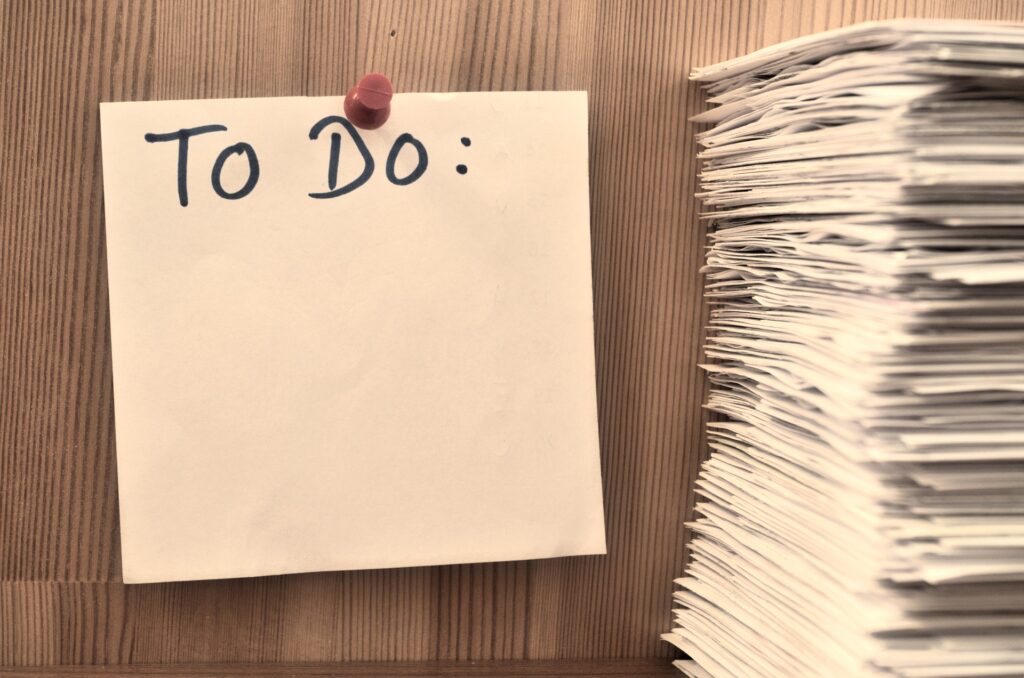

短くする努力はしたけどやっぱり長い…何かいい方法ない?
分割を細かくし、適切な重量を用いて効率的に疲労を与え、インターバルを管理をすればトレーニング時間はかなり改善されるでしょう。
特に分割を見直す効果は大きいですが、その分ジム通いの日数が増加してしまいます。
忙しく日数が確保できない人も少なくないでしょう。
そんな場合に活用できる次善の対策を3つ紹介します。
①カフェイン
②ダブルスプリット
③コンパウンドセット
なお長時間トレーニングにつきもののカタボリック対策についてはこちらのページで解説しています。
4-1 カフェイン
長時間トレーニングに起因する集中力の低下の対策として最もシンプルなのがカフェインです。
覚醒作用のあるカフェインを摂取することで、トレーニングの後半までダレることなく、ある程度の集中力を維持し続けることが出来ます。
(ブラック)コーヒーで摂取しても良いですし、それが苦手という場合はサプリメントがかなりリーズナブルな価格で売られてるのでそちらでもOKです。
但しカフェインの利用には注意点もあります。
まず1つ目が切れた瞬間に強い疲労感に襲われるということです。
カフェインはエネルギーを作ったり、疲労を取り除く原因があるわけじゃないことは覚えておく必要があります。
また頼り過ぎると効きが悪くなり、依存症のような状態になってしまう点も注意が必要です。
さらにトレーニングの時間帯によっては睡眠の質に悪影響を及ぼす可能性もあります。
4-2 ダブルスプリット
ダブルスプリットとは1日に2回トレーニングを行う方法で、朝食と昼食の間に1回、昼食と夕食の間に1回というのが一般的です。
平日にトレーニングの時間は取れないが、休日なら1日中空いているという偏りがある方にオススメの方法になります。
1回でまとめてしまうより1回のトレーニングにかかる時間が短くなり、集中力やカタボリックの問題を解消するのに有効な対策です。
ただし日を分けてトレーニングするのと同じパフォーマンスを発揮できるわけではありません。
それは疲労というのは脳が感じさせるものだからです。
また慎重に分割しても握力や体幹などは共通して使われることも関係しています。
なるべく高重量を扱うトレーニングを前半のパートに持っていき、特に後半のパートは負荷やセット数を無理ない範囲にとどめましょう。
仕事を挟んだ平日のダブルスプリットは精神的にもオーバーワークになる可能性があるので要注意です。
4-3 コンパウンドセット法
コンパウンドセット法とは複数の種目をまとめて1セットにする方法で、中でも2つの種目を組み合わせるスーパーセット法が有名です。
代表的なスーパーセットの例が上腕二頭筋と三頭筋の組み合わせで、アームカールとフレンチプレスを1まとめにしてセットを組みます。
そのほかにもこんな組み合わせもオススメです。
基本的にスーパーセット法では拮抗筋の関係にある部位をセットにします。
・大腿四頭筋とハムストリング
・腹直筋と脊柱起立筋肉
表裏の筋肉をバラバラに鍛えるよりもインターバルの時間が半分で済むので、ささやかですがトレーニング時間の短縮になります。
組み合わせることができる種目は多いので、ほとんどのトレーニングをスーパーセットにしてしまうことも不可能ではありません。
ただしコンパウンドセット法には注意点もあります。
1種目の1セットごとにインターバルを取るのに比べると疲労が大きく、集中力の消耗が大きいです。
また身体の疲労という意味では共通なので2番目にくる種目のパフォーマンスが低下しやすくなります。
日ごとに順番を入れ替えるなど工夫をするようにしましょう。
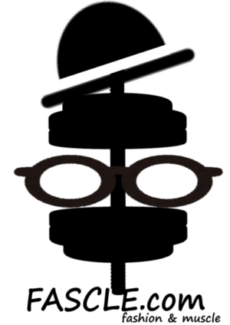
ベンチプレスとバーベルローイングでスーパーセットを組む猛者もいるよ(中級者以下にはオススメしません)
まとめ
長時間トレーニングの問題点とその対策について解説しました。
体質(カタボリック・アナボリックのしやすさ)には個人差があるため、トレーニング時間の正解も人によって異なります。
鍛えたい部位・範囲の広さ、トレーニングできる日数の影響もかなり大きいです。
時間を短くすることばかりに気を取られると、トレーニング内容が全体的に中途半端になる恐れもあります。
適切に対処すれば集中力の問題もカタボリックの問題も多少は改善できます。
必要最低限にする工夫は必要ですが、過度に時間を気にし過ぎる必要はありません。
1時間前後くらいに収まれば上々です。
かと言ってダブルスプリットやコンパウンドセット法で詰め込み過ぎると、オーバーワークの懸念もあります。
せっかく頑張っても精神的に疲弊して続けられなくなっては元も子もないので、その辺のバランスには注意しましょう。
てなとこで。
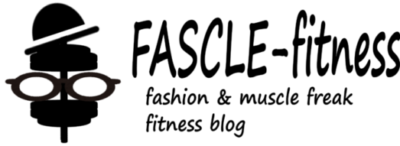



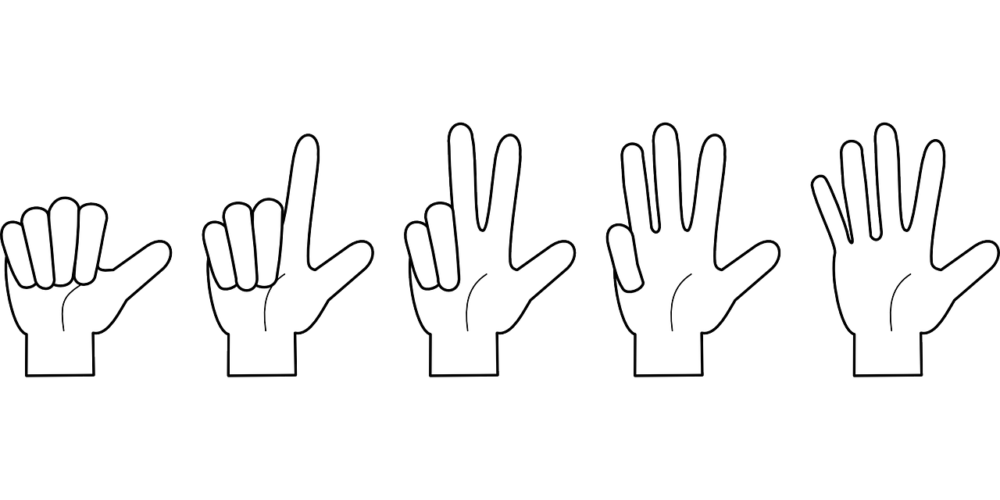








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません