関節・POF法・負荷の種類|筋トレ種目の分類方法とその特徴


山ほど種類があるけど結局トレーニング種目ってどれをやればいいの?
筋トレには山ほど種類がありますが、効率的に筋肉を発達させるためにはそれらを目的を持って適切に組み合わせる必要があります。
その組み合わせの基礎となるのが、筋トレ種目の分類・位置づけです。
このページでは主要なトレーニング種目の分類方法について解説します。
・トレーニング種目の代表的な分類方法
・分類ごとの特徴
このページで紹介する筋トレ種目の分類方法は以下の3種類です。
それぞれ順番に解説していきます。
①可動する関節数 ②筋肉に負荷がかかるポイント ③使用する器具
1 可動する関節の数による分類
まず1つ目が動作に関与(可動)する関節の数による種目の分類です。
関節の動きはその周辺にある筋肉の伸縮によって起こるので、可動する関節の数はそのまま関与する筋肉の数に影響します。
この分類は非常に大雑把で以下の2種類になります。
①単関節(アイソレート)種目 ②多関節(コンパウンド)種目
負荷の大きさと特定の部位への刺激のどちらを狙うか、その目的に合う種目を選ぶ上でこの分類は役に立ちます。
1-1 単関節(アイソレート)種目
トレーニング動作の際に1つの関節しか作用しない種目を単関節種目といいます。
アイソレートトレーニングとも呼ばれ、上腕二頭筋のアームカールなどが代表的な種目です。
腕や脚など身体の中心から離れた筋肉のトレーニングが多い傾向にあります。
可動する関節数(=関与する筋肉の数)が少ないので、扱える負荷はそれほど大きくありません。
その代わり狙った筋肉にピンポイントで負荷をかけやすいというメリットがあります。
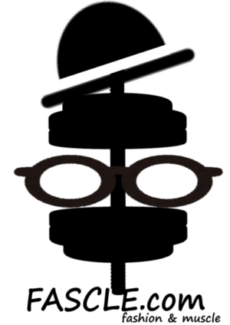
単関節だからと言って可動する筋肉が1つだけとは限らないよ
メリット:ピンポイントで狙える
デメリット:大きな負荷を扱えない
1-2 多関節(コンパウンド)種目
トレーニング動作の際に複数の関節が可動するトレーニング種目を多関節種目といいます。
複合関節種目やコンパウンドトレーニングとも呼ばれ、ベンチプレスやスクワットなどが代表的な種目です。
アイソレート種目と真逆で、胸や背中など身体の中心に近い筋肉のトレーニングが多い傾向にあります。
可動する関節数(=関与する筋肉の数)が多いので、大きな力を発揮して高重量を扱える点がメリットです。
一方で動作を上手くコントロールしないとメインではない筋肉に負荷が分散しやすくなります。
また協働筋の発達が甘いと、そこに足を引っ張られて重量が伸び悩む点もデメリットです。
メリット:高重量が扱える
デメリット:負荷が分散しやすい・協働筋の力に影響される
2 負荷がかかるポイントによる分類
筋肉に負荷がかかるポイントによる分類を略してPOF(Position Of Flexion)といい、これをベースにしたメニュー構成をPOF法と言います。
ポイントとは具体的には以下の3つです。
①ストレッチ種目 ②コントラクト種目 ③ミッドレンジ種目
このPOFの分類は以下の2つの点を考慮して種目を選ぶ上で有効です。
①筋張力のムラ ②筋肥大に有効な刺激
筋肉が可動域の端から端まで収縮する間に発揮する力にはムラがあります。
得意で強い筋力が発揮できるポイントと、苦手であまり力が出ないポイントとで、その差は非常に大きいです。
一番狙いたいポイントの筋力に合わせた負荷を選択する上でPOFの考え方が必要になります。

何で各ポイントにベストな負荷をかける必要があるの?
その理由が2つ目の筋肥大に有効な刺激を与えることです。
筋肥大のために有効な刺激は3つあり、ほとんどの部位において各ポイントと対応しています。
そのため全ての刺激を満遍なく与えるため、それぞれのポイントでベストパフォーマンスを発揮させる必要があるのです。
なおこの点については別のページで詳しく解説しています。
こちらの内容と併せて読むことで理解が進むはずです。
2-1 ストレッチ種目
最も筋肉が伸長したポイントで負荷がかかるのがストレッチ種目です。
筋肥大のスイッチの1つである筋繊維の微細な損傷が最も起きやすい負荷のかかり方です。
そのためトレーニング後の激しい筋肉痛(遅発性筋痛)の原因にもなります。
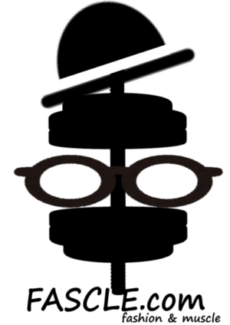
筋肉痛が出てるってことは、しっかりストレッチ出来てたってこと!
可動域を最大限に使う種目なので、広い範囲の筋繊維に一気に刺激を与える効果もあります。
他の種目では刺激しにくい筋肉の起始・停止(端っこ)まで刺激することが可能です。
メリット:広範囲を一気に刺激できる
デメリット:筋肉痛が残りやすい
2-2 コントラクト種目
最も筋肉が短縮したポイントで負荷がかかるのがコントラクト種目です。
筋肉が最も盛り上がったポイントの周辺で負荷がかかる種目なので、血管を圧迫することで筋肉を酸欠状態に追い込みやすい種目と言えます。
この酸欠状態も筋肥大のスイッチをオンにする効果的な刺激の1つです。
コントラクト種目は可動する関節数の分類で言うところの単関節種目であることが多く、ターゲットをピンポイントで狙えるというメリットもあります。
メリット:酸欠状態に追い込みやすい
デメリット:扱える負荷が小さい
2-3 ミッドレンジ種目
最大負荷のポイントがストレッチとコントラクトの中間に位置するのがミッドレンジ種目です。
筋肉の伸張状態としても完全にストレッチも短縮もし切っていない中間のポイントです。
ミッドレンジは可動する関節数の分類で言うところの多関節種目であることが多く、大きな重量を扱える種目でもあります。
ベンチプレスなど主要な高重量トレーニング種目はほとんどがこのミッドレンジ種目です。
最も直感的な筋肥大の要素である最大負荷をかけることが主な目的になります。
メリット:大きな負荷が扱える
デメリット:負荷が分散するリスクがある
ただ実は筋肉の種類とその動作(筋力発揮)の特性によっては必要ない場合もあります。
各筋肉の解剖学的な機能とその特徴について詳しくは別のページで解説してるので、そちらを参考にしてください。
3 使用する負荷による分類
最後がトレーニングに用いる負荷の種類による分類です。
筋トレに使用する負荷は大きく以下の3つに分けることが出来ます。
①フリーウェイト ②マシン ③その他
一緒くたにして考えられがちですが、これらの負荷はそれぞれ特性が異なっています。
特に1つ前の項目で紹介したPOFや筋肉に与える負荷の種類などを考えるに当たって不可欠です。
またジムに器具があり過ぎて何をやったら良いのか分からないという人も多いと思います。
狙いの重複を回避して効率的に筋トレするためにも重要な知識です。
3-1 フリーウェイト
ダンベルやバーベル、ケトルベルなど単純な重りがフリーウェイトです。
重りなので負荷は重力であり、知ってのとおり負荷は常に真下を向いています。
フリーウェイトトレーニングでは摩擦などの抵抗が基本的に生じません。
そのため設定した負荷が常に安定してかかり続ける点が主なメリットです。
一方で負荷の方向が真下しかないため、体勢を変えない限り動作の中でターゲットの筋肉に負荷がほとんど乗らないポイントが発生してしまいます。
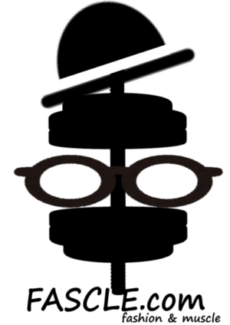
ベンチプレスのトップなんかが分かりやすいね
またウェイトの付け替えや持ち替えなどで時間をロスするため、ドロップセット法などにはあまり向いていません。
3-2 マシン
マシンと一口に言っても様々なパターンがあります。
ザっと挙げただけでも以下のとおりです。
①ウェイトスタック式 ②油圧式 ③電磁式
ウェイトスタック式というのはケーブルと滑車の先に重りがセットされていて、ピンの差し替えで重量を変更できるタイプのマシンです。
油圧式や電磁式はその名のとおり、油圧や電磁石の力で抵抗を生み出します。
程度の差はありますが、この3タイプは駆動部に摩擦などの抵抗が生じるため、負荷が一定ではありません。
一方で重量の変更が瞬間的に行えるため、ロス無く追い込みをかけられるというメリットがあります。
またチェストプレスなどのマシンは軌道が固定されてるため、フォームに不安がある人でも正確に効かせられる点もメリットです。
ケーブルマシンに関しては軌道の安定はありませんが、代わりに負荷の方向を自在に変えられるというメリットがあります。
つまりフリーウェイトの弱点をカバーできるってことです。
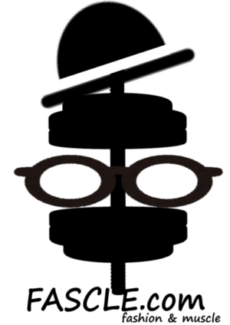
因みにハンマーストレングスとかはマシンとフリーウェイトの良いとこ取りって感じかな
| マシン種別 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ウェイトスタック式 (固定) | 負荷変更が楽 軌道が安定してる | ネガティブで負荷が減衰 |
| ウェイトスタック式 (ケーブル) | 負荷変更が楽 負荷の方向が自在 | ネガティブで負荷が減衰 |
| 油圧式 | 負荷変更が楽 軌道が安定してる | ネガティブで負荷が減衰 負荷が不正確(?) |
| 電磁式 | 負荷変更が楽 軌道が安定してる | ネガティブで負荷が減衰 負荷が不正確(?) |
| ハンマーストレングスなど (プレートをセットするマシン) | 軌道が安定している 負荷の減衰が少ない | ウェイト交換の手間 規格がアメリカン |
3-3 その他の負荷
オマケ的な感じですが、その他の負荷として自重・チューブがあります。
自重は言わずもがな自分の体重で、腕立て伏せやシットアップ(腹筋)、バックエクステンション(背筋)などです。
自宅で身1つで簡単に始められる点がメリットですが、負荷を加重出来ないので筋肥大効果には限界があります。
チューブトレーニングはケーブルマシンの代用として自宅でも行えるトレーニングです。
引っ掛ける場所などを工夫することでケーブルマシンと同様に負荷の方向を自在に変えることが出来ます。
ただし伸びるほど負荷が強くなり、その大きさが一定ではないため、POFを正確に狙うのはなかなか困難です。
いずれも手軽さが売りですが、トレーニング効果はそれなりなので、ジムに行けない日の補助として活用するものと考えておく方が良いでしょう。
まとめ
トレーニング種目の分類方法について解説しました。
分類方法は3つで、それぞれの利点は以下のとおりです。
①関節の可動 : 負荷の大きさとピンポイントのどちらを狙うか
②負荷がかかるポイント : どんなストレスをターゲットの筋肉にかけるか
③使用する負荷 : トレーニング環境の活かし方・POFに対応させる
これらはトレーニングで何を得たいかを考え、適切な切り口で種目を比較するために使うものです。
必ずしも全てを同時に使う必要はありません。
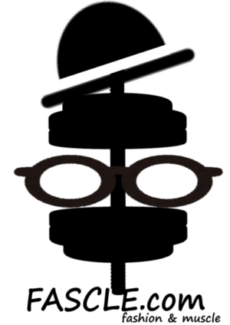
大抵はPOFをベースにして単関節と多関節のどっちを入れるか?って感じの使い方になるよ
これらの分類をベースにしたメニューの組み方や順番の設定については別のページで解説します。
そちらも参考にしてください。
てなとこで。
準備中
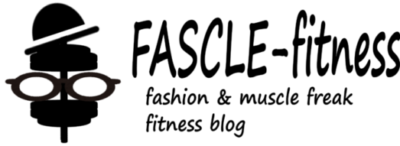












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません