低負荷トレのデメリット|筋肥大における筋力増加の重要性

かつては負荷の大きさこそが筋肉の成長に効果的とされていましたが、最近の研究では「低負荷トレーニングの方が効果的ではないか」とされています。
低負荷トレーニングの筋肥大への影響についてはこちらのページで解説しました。
最近は筋トレに限らずエビデンス重視の傾向が強く、このように研究で裏付けがある説の方が有力と考えられています。
しかし低負荷での筋トレが筋肥大のための最適解とは限らない可能性があることには注意が必要です。
このページでは、低負荷トレーニングの弱点・デメリットについて解説します。
・低負荷トレーニングの弱点
・最大筋力の重要性とは?
・低負荷トレーニング派が見落としている要素
1 低負荷トレーニングの弱点
低負荷トレーニングが筋肥大に有効とされるのはトレーニングボリュームが最大になるからです。
トレーニングボリューム(=総負荷量)は「負荷×回数×セット数」で決まります。
直感的には負荷が大きい方がこの値も大きくなりそうですが、負荷の増加以上にレップ数が減るので実際に計算してみると低負荷の方が大きくなります。
ただ低負荷トレーニングには「筋力の増加」という大きな弱点があるのです。
筋力は①筋肉の大きさ(断面積)と②運動神経の強度の2つの要素で決まります。
筋力には筋肉の大きさの影響の方が大きく、運動神経の影響は小さいというのが一般的な理解です。
しかし実際にはこの影響の度合いはシーンによって異なり、負荷が大きくなるほど運動神経の影響が大きくなっていきます。
低負荷でのトレーニングでも筋肥大は起きますが、運動神経の発達が伴わないためサイズアップに比例した筋力しか得られないのです。

運動神経の発達も伴うと10%のサイズアップに対して筋力は15~20%くらい伸びるよ
つまり最大筋力を伸ばすためには強い負荷をかけて運動神経を強化する必要があるということです。
そしてこの(最大)筋力が伸びにくいという点が低負荷トレーニングの最大の弱点になります。

確かに75㎏を10回挙げられる人が必ずしも100㎏を1回挙げられるわけじゃないもんね
2 最大筋力を伸ばす必要性


別に筋肉を強くしたいわけじゃないんだよなぁ…。
ボディメイクを目的に筋トレをしてる人の場合、このように思うかもしれません。
しかし筋力の増強は筋肥大においても大事な要素になるのです。その理由は大きく2つあります。
①トレーニングボリュームの増加 ②漸進性過負荷
2-1 トレーニングボリュームの増加
筋肥大にトレーニングボリュームの大きさが深く関わっていることは研究でも確認されていいます。
しかしそれだけで「筋力は無関係・低負荷トレーニングの方が効果的」と断言することは出来ません。
あくまで各人の筋力の範囲内において「低負荷×高回数」が効果的ということです。
最大筋力の強さが異なる2人を比較してみれば分かりやすいと思います。
<低負荷トレーニング(15RM)での比較>
①1RM=150㎏の人の場合
1セットの総負荷量は 100㎏ × 15回 = 1500
②1RM=80㎏の人の場合
1セットの総負荷量は 54 ㎏× 15回 = 810
つまり最大筋力が強いことはトレーニングボリュームの獲得においても有利ということです。
2-2 漸進性過負荷の理論
漢字アレルギーの人は見た目だけで読むのを辞めてしまいそうですが、見た目のいかつさに反して中身は非常にシンプルです。
これは筋肥大のためには与える負荷を少しずつ上げていく必要があるということを意味しています。
筋肥大は負荷という脅威から受けたストレスに反応して起きる防御反応です。
そのため外部から与えられるストレスが順応によって脅威と認識されなくなれば筋肥大は止まってしまいます。
負荷を徐々に増加させることはこの身体の慣れを予防する意味で重要になるのです。
しかし低負荷トレーニングに終始して一向に筋力が強くならなければ、負荷を上げていくことも出来ません。
ムリに過剰なウェイトを扱えばフォームの乱れやケガに繋がります。
低負荷は筋肥大に有効と言っても、時間の経過を加味すると必ずしもそうとは限らないということです。
まとめ
低負荷トレーニングに伴うデメリットについて解説しました。
トレーニングボリュームが重要という研究結果を参考にするならば、低負荷トレーニングが最も筋肥大に有効ということになります。
一方で筋力の増強という要素を捨てることになってしまうのです。
「ボディメイク目的であれば筋力は関係ない」と考えられがちですが、この考え方には非常に重要な視点が欠けてしまっています。
具体的には以下の2点で、いずれも筋肥大に重要なポイントです。
①筋力が強い方がトレーニングボリュームも大きくなる
②刺激の変化の幅が小さくなり、身体の順応が追いついてしまう
研究というのは予算の関係から実施できる期間には限界があります。
そのため低負荷トレーニングの方が効果的と結論づけた研究も一時点の変化にフォーカスしたモノになってしまっているのです。
言うまでもなく筋トレ・筋肥大は継続的に行っていくもので、一時的な伸びはさほど重要ではありません。
この時間の経過という視点が抜けてしまっていることが低負荷トレーニング派の最大の問題です。
しかしだからといってハイレップトレーニングに効果が無いということにはなりません。
筋肥大のためには「①トレーニングボリュームの確保」も「②筋力のアップ(運動神経の発達)」もどちらも重要になります。
そこで両者の折衷案としてよく用いられるのが中負荷のトレーニングです。
この方法のメリットやデメリットについて詳しくは別のページで解説します。ぜひ参考にしてください。
てなとこで。
準備中
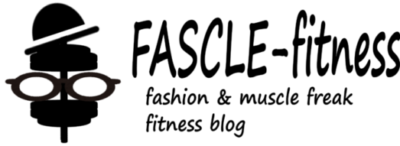









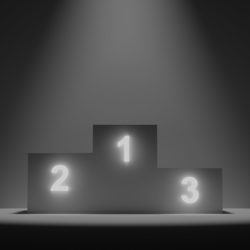

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません