【ダイエットの新常識】カロリー計算は無意味|エネルギー生成と代謝の関係
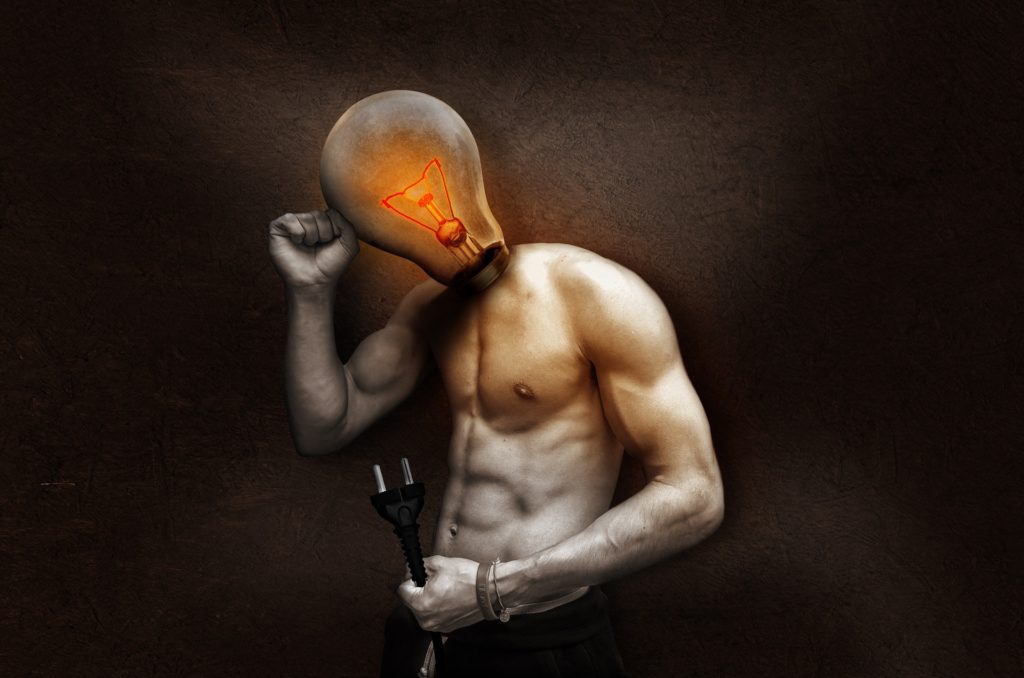
食事を減らすにしても運動を増やすにしてもカロリー計算はもはやダイエットの常識、誰もがやってるでしょう。
しかしエネルギー・カロリーは、ダイエットで頻繁に目にするワードですが、中身をちゃんと理解してない人は多いと思います。
実はそんな当たり前に行っているカロリー計算は無意味です。
面倒ごとから解放されたと考える人もいるでしょうが、ダイエットの手掛かりが無くなったと不安になる人もいると思います。
このページでは何故カロリー計算をする意味がないのか、意外とちゃんと知らないカロリーの真実について解説します。
・カロリー計算が無意味な2つの理由
・そもそもなぜカロリーが導入されたのか?
・意味がないだけじゃないカロリーの問題点
・人間の本当のエネルギーとは
1 ダイエットにカロリー計算は無意味
冒頭でも触れた通りダイエットをする上でカロリー計算をしても無意味です。
まずはその理由を解説します。理由は以下大きく2つです。
①カロリーは人間のエネルギーの単位ではない
②正確に把握するのはムリ
1-1 人間は汽車じゃない
カロリーというのは、実際に栄養素を燃やした時に発生する熱を表したものです。

だから「熱量」って表記されることもあるよね
人間の身体は機関車とは違います。
体脂肪を「燃やす」などと表現されることはあっても、体内で実際に食べ物が燃えてるわけじゃありません。
体温の上昇のように身体で発生する熱は活動の結果であってエネルギーのもとではないのです。
その証拠にタンパク質にもカロリーはありますが、血肉の材料であり基本的には活動のエネルギーにはなりません。
厳密に言うとタンパク質からもエネルギーを合成することは出来ます(糖新生)。
ただし1g当たり4kcalで同じはずの糖質から作られるエネルギーの1割程度です。
余分が体脂肪として蓄えられるのは確かですが、その蓄えられるモノもやはりカロリーではありません。
このエネルギーというのが何かについては後半で解説します。
1-2 カロリーを正確に把握するのはムリ
仮に「カロリー=エネルギー」だったとしたら摂取エネルギーは秤を使えば正確に把握できるでしょう。
カロリー計算がメンドウなら最初から表示されてる加工食品を買えばOKです。
加工食品まみれの生活が肥満はもちろん様々な健康問題に繋がることは言うまでもなく現実的ではありませんが…。
一方の消費エネルギーの方はどうでしょう?消費でまず意識されるのは運動性代謝です。
代表的な運動、例えばジョギングや水泳などの消費カロリーは示されてますが、あれはあくまで目安です。
時間当たりで換算されてることが多く、スピードや1歩や1掻きの効率は考えられていません。
通勤で何歩、何分歩いたか、電車で立ってた分で1日にどれだけ消費したかなど計算できますか?
さらに運動性ではない代謝は固定と考えられてますがこれは誤解です。
体組成計などで計れる基礎代謝などは体重と身長から推計されただけのものに過ぎません。
実際には1日の運動量などの影響で安静時の代謝量もかなり大きく変化します。
つまり一生懸命に食事の摂取カロリーを計算したところで、消費の方が正確じゃないので何の意味もないということです。
2 カロリーを厳格に管理すれば痩せる?
「そうか!管理が甘かったから痩せなかったんだ!」と思った人、残念ながら違います。
方法の精度ではなく、そもそも方法自体に効果がないから痩せないだけです。
2-1 カロリー計算のお陰に見えるだけ
ボディビルダーや計量のあるスポーツ選手は厳格にカロリー管理をすると言いますね。
彼らを例に取るとやはりカロリー管理が効果的かのように思えるかもしれません。
しかしスポーツ選手が食事で体重コントロールができるのはカロリー管理のお陰じゃなく、食事内容のお陰です。
何をどう食べる(食べない)かが重要なのであって、それを守ってるスポーツ選手には本当はカロリー計算は不要なのです。
2-2 厳格に管理するとどうなるか
厳格な食事制限で体重を調整すると言えば格闘家やボディビルダーでしょう。
確かに彼らの身体は本番はバキバキです。
しかし大抵のスポーツ選手はいつでもある程度のスタイルを保つ一方で、彼らは試合後に体型崩れを起こします。
増量期などと言って自分でコントロールしてるつもりですが、体重の増加の大半は単なるリバウンドによるものです。
これは厳格にカロリーを管理して、収支をマイナスにしようと食事を削った代償です。
食事制限は短期的には体重を減らす効果がありますが、必ず反動が起こります。
プロだろうと一般人だろうと、厳格だろうがなかろうが、カロリー管理で痩せる効果は一時的ってことです。
3 カロリーを無視したくなる事実
増量・減量がカロリーで説明されるようになってから相当な時間が経ちました。
生まれた時から食品表示にカロリー表記があったって人も多いでしょう。
そんなカロリーネイティブ世代にはカロリー無意味説は受け入れがたい考え方かもしれません。
なかなかカロリーを無視できないという人のためにカロリー信仰を辞めたくなるような事実を2つ紹介します。
①カロリー導入の経緯 ②研究が示すカロリーの無意味さ
3-1 そもそもカロリーは何故導入されたのか?
カロリーがここまで世間に浸透するようになった発端の闇がけっこう深いので、まずそれを紹介します。
カロリーという考え方を世に広めたのはアメリカのフーバー政権下の食品局です。
当時のアメリカでは心臓病での死亡者の増加が顕著になっていました。
この問題の本当の原因は平均寿命が延び、心臓の疾患が顕在化する年齢まで生きる人が増えたことです。
寿命の延伸について触れられることはなく、生活習慣なかでも特に食習慣に問題があると考えられました。
血管との関係で脂質・コレステロールに焦点が当てられます。

いわゆるコレステロール犯人説ね
ここで1つの不都合が生じてしまいます。
当時から心臓病と相関のある肥満の原因は炭水化物というのが常識だったのです。
この矛盾を解消し脂質を悪にするための論拠として使われたのがカロリーなのです。
知っての通り脂質のカロリーは1g当たり9kcalと炭水化物の2倍以上あります。

「こんなにカロリーが高いんだから身体に悪いにきまってるでしょ」って感じか…
結果的に以下のような認識を広めることになりますが、ちなみに科学的な検証は一切されていません。
特定の栄養素の問題ではなくカロリーの摂り過ぎが肥満の原因なのだ
つまり脂質の摂取を控えることはカロリー制限に有効で肥満と心臓病の予防に効果的である
こんな詰めの甘い理論だけでエビデンスのない「常識」が広まってしまったのです。
3-2 国の意図とは真逆のデータが沢山
この理論を補強するために低カロリー・低脂質食のダイエット効果を検証する研究が何度も行われました。
しかしいずれの研究においても体重減少効果は確認されてません。

自分たちの理論を何百万ドルもかけて否定し続けているって皮肉な話だよね
国の指導に多くの国民が従った結果、20年間で食事・消費活動は大きく変わりました。
摂取カロリーに占める脂質の比率は45%から35%に減り、バターは38%、肉類は13%、卵は18%減っています。
その代わりに炭水化物の摂取は増え、総摂取カロリーは抑えられました。
それでどうなったか?残念ながら心臓病はそんなに減りませんでした。
それどころかアメリカの肥満基準であるBMIが30を超える人が激増していました。
実験室の中だけでなく、現実世界のビッグデータにもカロリー(脂質)犯人説は否定されたのです。
ちなみにカロリー理論が持ち出されてからというもの、摂取カロリーは一貫して減少しています。
「食の欧米化でカロリーが増加した」というのは単なるイメージ論で実は誤解です。
肥満の多い現代人の方が、肥満なんて問題の存在しなかった1970年以前より摂取カロリーは圧倒的に低いのです。
4 カロリー理論の罪深さ
摂取カロリーが減ってるのに太っていくという事実は、カロリー理論が無意味という指摘にとどまりません。
カロリーという外側を重視させ、その中身への意識を逸らしてしまうという点が大きな問題です。
食品表示に書かれてるカロリーの足し算をして、帳尻を合わせればいいという簡単さがそれを助長しています。
結果として「同じカロリーならどの栄養素・食品から摂っても同じ」という誤解を生むことになってるのです。
ここまで言われれば誰もが「それはおかしい」と気付きますが、逆に極端に説明されるまで誰も気付きません。
汽車が石炭の産地や品種にこだわらずに走るのと違って、人間の身体は非常に複雑です。
三大栄養素のバランスをとること、さらにその栄養素をどんな食品から摂るかも非常に重要になります。
この「何を食べるか」こそが肥満を左右する根本なのです。
こうしたよく考えれば当然かつ重要な事実から目を背けてもいいような気にさせる点でもカロリー理論は罪深いものです。

こういう意味では「カロリーのせいで太る」と言えなくもないね
5 人間のエネルギーは何?
では人間の活動に使われるエネルギーとは何なのか?最後にそれを解説します。
身体の活動のエネルギーは糖質由来のATP(アデノシン三リン酸)と脂質由来のFFA(遊離脂肪酸)の2つです。
このうち特にATPが特にメインのエネルギーになります。

超厳密に言うとATPをADPとリンに分解する時に生じるエネルギーを使うんだけどね
ATPは全身に無数に存在する細胞内のミトコンドリアという微生物の活動で生成されるものです。
ダイエットでよく言われる代謝の良し悪しとは食べ物の栄養素をエネルギーに変換する効率のことで、ATPの産生という点ではミトコンドリアの活性化が重要になります。
代謝が上手く回ることで食べた物が体脂肪よりもエネルギーになりやすく、エネルギーが豊富なので疲れにくくもなります。
なお代謝を向上させる方法について詳しくは別のページで解説してるので、参考にしてください。
まとめ
ダイエットの基本となっているカロリーが無意味であることについて解説しました。
カロリー収支をマイナスにすることがダイエットの常識ですが、そもそも摂取カロリーや消費カロリーを正確に把握することは出来ません。
つまりたとえカロリーが役に立つ指標だったとしても現実的ではないってことです。
本文で解説したとおり、カロリーがダイエットや健康の領域に導入された経緯はかなりこじ付け感が強いものです。
そしてその効果を検証しようとした研究でも軒並み否定的な結果が出されています。
結局のとこ役に立たない指標ということです。

肥満が深刻な現代人の方が摂取してるカロリーが少ないってのは決定的だね
カロリーを意識し過ぎるあまり栄養素や食品の偏りが起きることも多いため、問題が大きいです。
時系列で食事量の多寡を把握するくらいには使えますが、厳密な管理はする意味がありません。
てなとこで。
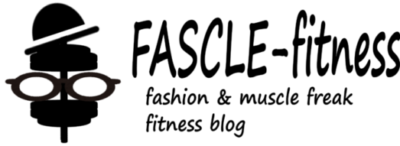











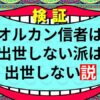
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません