減量期の食事|カラダを絞るためのカロリー計算の方法と問題点

ボディメイクをするに当たって定期的な減量は欠かせません。
減量期・増量期と明確にシーズン分けを行う重要性についてはこちらのページで解説しています。
減量期においては日頃からハードに筋トレを行ってるトレーニーの場合、運動強度やボリュームを上げるよりも食事のコントロールが重要になります。
では減量中には実際どれくらいのカロリーを摂取すれば良いのでしょうか?
このページでは減量の基本中の基本である減量カロリーの計算方法について解説します。
・減量期の摂取カロリーの計算方法
・一般的な減量カロリー計算の問題点
・代案としてのカロリー計算の方法
1 減量期のカロリー摂取

減量期は身体(主に体脂肪)の分解を目指すので、カロリーは当然減らしていきます。
ただ増量期・減量期を通じてトレーニー・ボディメイクの最大の目的は筋肉を増やすことです。
体脂肪の減少を意識しすぎるあまり、闇雲にカロリーを減らして筋肉まで分解してしまっては元も子もありません。
適正な摂取カロリーを目指すのか、そしてどのような栄養バランスで摂取すべきなのかまでしっかり理解しましょう。
まず減量中に1日で摂取するトータルカロリーの大きさを計算します。
ざっくりとした流れは以下の通りです。
①基礎代謝の計算
↓
②メンテナンスカロリーの計算
↓
③減量中の摂取カロリーを計算
1-1 基礎代謝の計算
基礎代謝は熱の発生や消化、脳の活動など意識していなくても消費するカロリーの総量です。
ここを下回ってしまうと生命活動の維持に問題が生じるので、代謝などが極端に落ちて減量の効率が逆に落ちてしまいます。
そのためここの水準は絶対に守らなければいけません。
計算方法は以下の通りです。ちなみにハリスベネディクト方程式と言います。
13.4 × 体重(㎏)+ 4.8 × 身長(㎝)- 5.68 × 年齢(歳)+ 88.4

方程式の名前は全く覚える必要はないよ
例えば30歳、身長175㎝、体重70㎏の人の場合はこんな感じになります。
13.4 × 70 + 4.8 × 175 - 5.68 × 30 + 88.4 = 1,696kcal
1-2 メンテナンスカロリーの計算
メンテナンスカロリーは現状の身体を維持するために必要なカロリーのことで、基礎代謝に運動などの影響をプラスした1日のおおよその総消費カロリーです。
これを上回れば増量し、下回れば減量になります。
メンテナンスカロリーは計算した基礎代謝に活動量に応じた指数をかけることで計算でき、この指数を運動強度依存定数と言います。

これも名前は覚えなくていいよ
<運動強度依存定数>
①デスクワーク中心で普段はほとんど運動しない人 → 1.2
②強度の低い筋トレを週に1~3回する人 → 1.375
③やや強度の高い筋トレを週に3~5回する人 → 1.55
④強度の高い筋トレを週に6~7回する人 → 1.725
⑤強度の高い筋トレを1日に2回するor肉体労働をして毎日強度の高い筋トレをしている人 → 1.9
基礎代謝量 × 運動強度依存定数 で算出されるのがメンテナンスカロリーです。
サラリーマントレーニーの場合は②~④辺りが多いでしょうか?先程の基礎代謝で計算します。
1,696kcal × 1.55 = 2,628kcal
成人男性の1日の必要摂取カロリーなどの指標はかなりアバウトなので、しっかり計算しましょう。
多過ぎれば減量になりませんが、少なすぎても筋肉を落とすリスクが高くなってしまいます。
因みに①~⑤の運動強度のいずれにも該当しないという人も多いかもしれません。
そういう場合、ぼく個人としては提示されてない中間の数字を入れても良いと考えています。
と言うのも、そもそも筋トレの「強度」というのが主観的でかなりアバウトな指標だからです。
摂取した栄養素の吸収効率もコンディションによって異なるので、数キロカロリー単位でシビアに計算する意味はあまりありません。

「強度が高い筋トレを週5回なら1.675」みたいな目分量でOKだよ
1-3 減量中の摂取カロリーは?
メンテナンスカロリーは現状維持のためのカロリーなので、これを下回るカロリーを設定すれば痩せます。
ただし極端に減らしてしまえば体脂肪だけでなく筋肉も分解されてしまうので、減らす幅は慎重な検討が必要です。
理想的な減量ペースはひと月に体重の3~5%までとされています。
つまり体重70㎏の人の場合は月に2.1~3.5㎏程度ということです。意外と小幅ですよね?
体脂肪のカロリーは1g当たり7~9kcalなのでカロリーにすると14,700~31,500kcalです。
1ヵ月でこれを削るので、30日で割ると1日の摂取カロリーは490~1050kcalだけ削るということになります。

これはあくまで「最大で」ってことには注意!
計算方法は以下の通り。
体重(㎏)× 3(%)÷ 100 = 1ヶ月の減量幅(㎏)
1ヶ月の減量幅(㎏)× 7(kcal)÷ 30(日)= 1日にカットするカロリー(最大値)

脂質のカロリーって9kcalじゃないの?
確かに脂質のカロリーは9kcalですが、体脂肪(=中性脂肪)は純粋な脂質ではありません。
なので9kcalで計算してしまうと削りすぎてしまう可能性があります。
おおよそ7kcalで計算するというのが一般的です。

糖質と脂質の合成物だからね!
2 一般的な減量カロリーの計算方法の難点

一般的な減量期のカロリー計算の方法を紹介しましたが、この方法には問題もあります。
それはカロリーを算出するために用いた要素に関して以下のような難点があるからです。
①メンテナンスカロリーの計算がアバウト過ぎる
②基礎代謝は固定されている数字ではない
2-1 メンテナンスカロリーはかなりアバウトな数字
まず第一に既に軽く触れた通りメンテナンスカロリー(運動強度依存定数)の算出はかなりアバウトなものです。その原因は以下の2点にあります。
①強度の判定が主観的
②5つの分類のいずれにも属さないパターン
数字自体は科学的なエビデンスに基づくものですが、その判定を行う「強度」というのがかなり主観的な指標です。
あまり根性がないタイプなら客観的には弱い強度でも高強度と判定してしまいます。
逆にストイック過ぎれば超高強度でも弱いと判定してしまう可能性もあるでしょう。
いずれにしてもメンテナンスカロリーの算出を誤ってしまいます。
また自分の活動パターンが①~⑤のどれにも当てはまらなかったという人も多いはずです。
軽い調整であればザックリ目安で数字を入れても良いですが、しっかり絞りたい場合は目分量ではいけません。
この点でも全幅の信頼を置くことは出来ない指標と言えます。
2-2 基礎代謝は固定されてない
さらにメンテナンスカロリーを算出するベースになる基礎代謝の方にも問題があります。
一般的な方法では基礎代謝は年齢や身長など固定の数字で計算しました。
この計算方法でもある程度の基礎代謝を把握することは出来ますが、あまり正確ではありません。
最近の研究で代謝量というのは時々刻々と変化し続けているということが分かっています。
「運動量を増やせば消費カロリーが増えて痩せる」というのが長年ダイエット界の常識でした。
しかし実際には運動によって活動代謝が増加すると、その分を吸収するように安静時(基礎)代謝の低下が起こります。
つまり体重や身長、年齢などの固定された数字から算出した基礎代謝はそもそもあまり当てにならないということです。
その他にも食事誘発性熱産生(DIT)のように、食べた物によって消費するカロリーが異なる要素もあります。
このことからそもそも基礎代謝量を正確に把握しようとすることにムリがあると言えるでしょう。
3 減量カロリーの計算方法の弱点をカバーする方法

以上で見てきたとおり基礎代謝やそれに付随するメンテナンスカロリーは変化し続けるものなので、厳密に追うのは非効率です。

と言うより計算で正確に算出しようとするのが現実的じゃないよね
ではどのようにして減量時のカロリーを把握すれば良いのでしょうか?
この一般的な計算方法の弱点を補う方法が2つあります。
①増量期間中の体重増加から減量カロリーを逆算する
②活動量計を使って毎日の消費カロリーを把握する
3-1 増量期のカロリーから減量期のカロリーを逆算する方法
1つ目がメンテナンスカロリーを増量期の体脂肪の増加分から計算するという方法です。
例えば2ヵ月間の増量で体重が60㎏から70㎏に、体脂肪率が8%から15%に増えた場合の体脂肪の増加は以下のように計算できます。
60(㎏)× 8(%)÷ 100 = 4.8㎏
70(㎏)× 15(%)÷ 100 = 10.5㎏
10.5kg - 4.8kg = 5.7kg
つまり今回の増量期間での体脂肪の増加は5.7㎏ということです。
脂質1g当たりのカロリーは7kcalなので、この2ヵ月トータルでの余剰カロリーは以下のように計算できます。
5,700(g)×7(kcal)=39,900kcal。
1日当たりに換算すると39,900 ÷(30+31)= 654kcalの余剰ということです。
つまり現在の摂取カロリーからこれを削ることで現状維持になるので、その数字がメンテナンスカロリーになります。
この計算方法を簡単に解説してくれてる動画も見てみてください。

あくまで平均だけど、これくらいシンプルな方が負担が小さいよ!
3-2 活動量計を使ってカロリーを計算する
増量期のカロリーから逆算する方法は非常に画期的ですが、やはり完全ではありません。
というのも減量による体重や筋肉量の減少によってメンテナンスカロリーが変化していくからです。
基礎代謝は固定の数字で正確に計算することが出来ないと解説しましたが、これは体重が基礎代謝に無関係ということではありません。
当然のことながら身体の大きい人の方が消費するエネルギーは大きくなります。
つまり増量期から減量に入るに従ってメンテナンスカロリーも低下していき、減量カロリーが当初から徐々に低下していくということです。
そうした身体の変化に伴う必要カロリーの変化を捕捉するために併用したいのが活動量計です。
安価なモノだと数値の正確性に難があるのでやや高い買い物になりますが、より厳密な減量を進める上での必須アイテムになります。
オーラリングは正確性も高く、指輪型で普段からつけてても邪魔にならないので睡眠の質の計測などにも使えるでしょう。

もちろん高いモノだからって完璧じゃないからあくまで併用が基本だよ
まとめ
減量中のカロリー計算の方法について解説しました。
一般的な方法、その難点、それをカバーする代案など、カロリー計算の方法は1つではありません。
以下に紹介した方法をまとめます。
①一般的な方法:基礎代謝 → メンテナンスカロリー → 減量幅だけカロリーを削る
②増量幅から逆算:増量期間と体脂肪の増加 → 1日当たりの余剰カロリー → メンテナンスカロリー
③活動量計を使う:体重の減少や活動量によって時々刻々と変化する消費カロリーを捕捉する
どれが正解とか、どれか1つだけに絞るのではなく、これらを併用して正確性を高めていくというのが良いと思います。
また減量や増量においてカロリーを重視する傾向は強いですが、どんな栄養バランスで摂取するか、そしてどのような食品から摂取するかが意外と重要です。

あと食べ方もね
これらのカロリーに比べると軽視されがちな要素について詳しくは別のページで解説します。
トータルで配慮して減量を成功させましょう。
てなとこで。
準備中
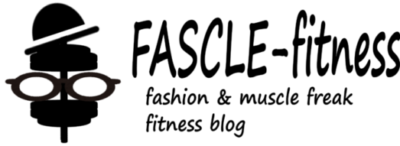


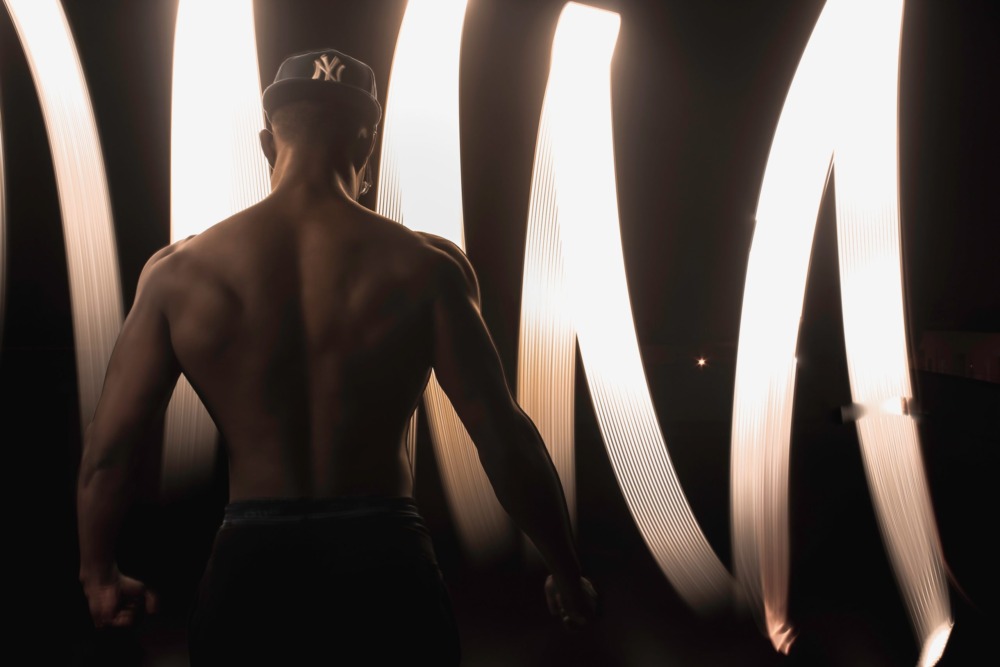








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません