【フェーズ分け】非線形ピリオダイゼーション・マンデルブロトレーニングのやり方


マンデルブロトレーニングの具体的なやり方を知りたい!
一般的な線形ピリオダイゼーションよりも非線形ピリオダイゼーションの方が効果が高いことが研究でも実証されています。
具体的なメリットについてはこちらのページをご覧下さい。
このページでは非線形ピリオダイゼーションの中でも代表的なメソッドであるマンデルブロトレーニングのやり方について解説します。
筋肉博士こと山本義徳先生の指導でも有名な方法です。
・マンデルブロトレーニングのフェーズ分けの方法
・効率化する(?)テクニック
・テクニックに対するぼくの考察
・マンデルブロトレーニング実践上の注意点
1 マンデルブロトレーニングのフェーズ分け
非線形ピリオダイゼーションは複数の種類の負荷・レップ数をローテーションする方法です。
それぞれの設定のことをフェーズと呼びます。
このフェーズはRM法をベースにして3~4つ設定するのが一般的です。
4つのフェーズをセットする場合は以下のようになります。
①中負荷 ②高負荷 ③低負荷 ④超低負荷
因みに山本義徳先生の場合は3フェーズ構成です。
負荷の大きさとレップ数によって筋肉に与える刺激・ストレスの種類が異なります。
それらを満遍なく機械的にローテーションして与えることで様々な効果をカバーしつつ、身体が刺激を予想できないようにするのが狙いです。
以下の表に各フェーズの狙いと順番をまとめました。
山本義徳先生式で3フェーズにする場合は、この表の③低負荷フェーズを抜くだけで、順番はそのままでOKです。
| フェーズ① | フェーズ② | フェーズ③ | フェーズ④ | |
|---|---|---|---|---|
| 負荷の大きさ | 中負荷 8~10RM | 高負荷 3~5RM | 低負荷 12~15RM | 超負荷 20~30RM |
| 狙うストレス | メカニカルストレス (筋肥大寄り) | メカニカルストレス (筋力寄り) | トレーニング ボリューム | メタボリック ストレス |
| セット数 | 2~4セット | 3~4セット | 4~5セット | 5~6セット |
| インターバル | 長い 1分半~2分半 | かなり長い 3~5分 | 短い 1~1分半 | かなり短い 30~45秒 |

因みにフェーズ③を入れてるのは、16RM以上の負荷には筋肥大効果が無いって研究があるからだよ
2 マンデルブロトレーニングのテクニック?
マンデルブロトレーニングにはテクニックと言われるものがあるので紹介しておきます。
2-1 具体的なテクニック
それは部位ごとにフェーズをずらすという方法です。
基本の方法では、その週は全ての部位で同じフェーズ(負荷レベル)を行うことになります。
しかしこの方法だとフェーズ②やフェーズ④のような極端な設定における負担がかなり大きいのです。

特にフェーズ④はイメージに反してめちゃキツい…
その疲労を分散させるために、部位または分割ごとにフェーズをずらして回すということです。
3分割だった場合の流れを表にしました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割① フェーズ① | オフ | 分割② フェーズ② | オフ | オフ | 分割③ フェーズ③ | オフ |
| 分割① フェーズ② | オフ | 分割② フェーズ③ | オフ | オフ | 分割③ フェーズ④ | オフ |
2-2 テクニックとしては微妙…
因みにぼくはこの方法をあまりオススメしません。
理由は大きく以下の2つです。
①管理の手間がかかる ②マンデルブロのメリットが消える?
まず日ごとの管理が複雑になるからです。
分割ごとに分けるパターンは分割数がフェーズの数と一致するなら多少シンプルですが、分割数が異なったり部位ごととなると覚えておけません。
筋トレだけでも十分時間を使うのに、管理の手間まで増えるのはキツいです。

なるべく余計なことに頭使ったり手間かけたりはしたくないかな…
もう1つ、身体の慣れを防止するというマンデルブロトレーニングのメリットが薄れる可能性があります。
分割法で鍛える部位が変わっても身体としては一体なので、負荷をコロコロ変えてしまうと様々な刺激に適応してしまうからです。
そもそも通常のトレーニングであれば、全ての分割・部位で負荷・レップ数はずっと通しで同じはずです。
これをマンデルブロトレーニングだから、と特別に扱いを変える理由はないと思います。
3 マンデルブロトレーニングの注意点
割りとやることもシンプルで、かつ筋肥大効果が高いとされるマンデルブロトレーニングですが、実施する上で2つ注意点があります。
具体的には以下のとおりです。
①全種目で同じ負荷レベル ②順番は絶対
たまにある勘違いが、1回のトレーニングで種目ごとにフェーズを変えてしまうというものです。
これはこれで効果的なトレーニングではありますが、マンデルブロトレーニングではありません。
例えば、ある部位を3種目でメニューを組んでるとしたらフェーズ①では全ての種目で8~10RMを扱います。
そして次回のトレーニングでは全ての種目で3~5RMを扱う、といった感じです。
もう1つフェーズの順番は必ず守らなければいけません。

理由は適応と疲労回復の2つがあるよ
負荷の大きさへの段階的な適応というのが1つ目の理由です。
フェーズの中で身体がそちらに慣れてしまうため、特に低負荷の直後に高負荷を行うなどはケガの原因になります。

筋肉だけじゃなく身体全体の負担まで大きくなっちゃうってことか
また関節の疲労回復という点も考慮してフェーズの順番が設定されています。
高負荷の後に中負荷を行ってしまったりすると、強度が強く回復が出来ません。
ケガのリスクはもちろんパフォーマンスも上がりにくくなるので注意しましょう。
まとめ
非線形ピリオダイゼーションの代表格であるマンデルブロトレーニングのやり方について解説しました。
3~4個のフェーズを設定し、決められた順番でローテーションしていくだけです。
守るべきポイントは2つだけ。
まず全ての種目で同じフェーズ(負荷レベル)に取り組むこと。そして順番を必ず守ること。
これさえ守ればOKです。
高負荷のフェーズ②もさることながら、超低負荷のフェーズ④もなかなかのキツさです。
疲労が残っていてパフォーマンスが上がらなくては元も子もないので、回復のためのオフも適切に確保しましょう。
てなとこで。
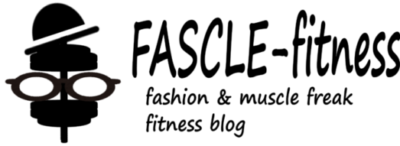











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません