三角筋中部を効果的に鍛えるトレーニング方法|種目とテクニック【肩幅を広くする】

三角筋の中部(ミドルデルタ)はフィジーカーに限らずトレーニーが憧れるパーツです。
丸みのある肩、いわゆるメロン肩を形作る上で不可欠の筋肉ですが、実は上手く発達しにくい部位でもあります。
他の筋肉に負荷を逃がさず、効果的に筋肥大させるために必要な基本については以下のページで解説しました。
基本機能を押さえた上で、このページでは三角筋中部(ミドルデルタ)の具体的なトレーニング種目について解説します。
・三角筋中部(ミドルデルタ)を鍛えるトレーニング種目
・トレーニング種目の選択、メニュー構成の方法
・各筋トレ種目のポイント、テクニック、注意点
・悩む人の多い僧帽筋の関与を減らすためのポイント
・参考になるトレーニングテクニックを解説した動画
三角筋中部を鍛えるトレーニング種目

三角筋の中部を鍛えるのに効果的なトレーニング種目を動画とともに紹介します。
三角筋中部の解剖学的な機能は肩関節の外転動作のみです。
そしてこの外転動作は最大筋力を発揮するポイントがストレッチポジションに一致します。
つまり筋肥大の3大要素をベースに種目を選択するならストレッチ種目とコントラクト種目の2つが中心です。
種目やテクニック、バリエーションも色々紹介しますが、これをベースに環境や反応を見て種目を選択してください。
種目にバリエーションを持たせる重要性については以下のページで解説しています。
また筋肥大に必須の3大要素についてはこちらのページを参考にしてください。
いつまで経っても発達しない人にありがちなミスなども解説するので参考にしてください。
サイドレイズ
サイドレイズは三角筋の中部の解剖学的な機能である肩関節の外転動作そのものです。
別名ラテラルレイズとも言われ、三角筋の中部を鍛える種目として誰もが知る超有名なトレーニングです。
POFの分類ではコントラクト種目に当たります。
直感的かつ直接的にアプローチできる種目のはずですが、その一方で多くの人が上手く効かせられないと悩む種目でもあります。
上手く効かせられない原因とその解決策についても紹介するので、悩みが解消できるはずです。
まずは基本中の基本のスタンディングで行うスタイルから紹介します。
基本的なフォーム
まずは基本の動作フォームから紹介します。
【準備】
① 脚を肩幅に開いて立ってダンベルを両手に持つ
② 両肘を軽く曲げ、肩甲骨を寄せて下げる(肩甲骨の動作と僧帽筋の関与を抑える)
【動作】
③ 肩甲骨の姿勢を維持したままTの字を作るように両脇を開いて挙げていく
(上に挙げるよりもダンベルを遠くに挙げて弧を描くイメージ)
④ トップポジションで1~2秒キープ
⑤ ゆっくりと下ろし、負荷が抜ける前に動作を切り返す
⑥ 繰り返し
肩甲骨は多少動いてもいいですが、あまりに頼り過ぎると負荷が僧帽筋に乗ってしまうので注意しましょう。
筋肉の走行方向に沿った角度で動作する必要があるので、厳密には「体側で真っ直ぐ上に」ではありません。
自分の筋肉の走行と同じ角度で、肩の真横よりやや斜め前にダンベルを放るイメージです。

15~30°くらいの「やや」斜めで十分!
サイドレイズのバリエーション
筋肉(の走行)の向きを重力の向きに一致させるために前傾するというスタイルもあります。
前傾する角度は三角筋の斜め具合によって変わり、これは個人差があるので観察は必須です。

こっちも大体10~15°くらいになるはずだよ!
体幹を維持するのに意識を取られて可動がブレる場合はリーニングサイドレイズにしましょう。
リーニングサイドレイズは別名ワンハンドサイドレイズです。
片方だけで動作をして、もう一方の手は何かに掴まって身体を安定させます。
片手でやる分、収縮を強く意識することが出来る一方で時間がかかるというデメリットもあるのが難点です。
フルカンかエンプティカンか?
サイドレイズで議論になるのがダンベルを持つ手の角度です。
もっと正確に言えば親指が上(フルカン)か小指が上(エンプティカン)か。
かつては小指を上にするエンプティカンの方が効果的かつ故障リスクも低いとされていました。
しかし現在では親指を上にするフルカンの方がケガのリスクが低いとされています。
【補足:フルカン・エンプティカンの由来】
フルは「いっぱいの」の意味でエンプティは「空の」という意味です。
何が空かと言えばカン(缶)の中身のこと。
フタの開いたジュースの缶を持ってサイドレイズをするとき、親指が下だと中身がこぼれてしまいますよね?
一方で親指を上にしていれば中身は残るはずです(フルとはいきませんが…)。
ここから親指を上にするスタイルをフルカン、下にするスタイルをエンプティカンと呼ぶようになりました。
ちなみに握り方で言うと親指の位置も意外と重要になります。
というのも肩関節の外転動作には、やや意外ですが上腕二頭筋が関与するのです。
親指寄りの指は上腕二頭筋に繋がる正中神経が支配してるため、ここに力が入るってことは同時に上腕二頭筋が働きやすくなります。
そこで有効なテクニックが親指を外すオフサムグリップで、これは広背筋トレーニングでも有効です。
ただでさえ僧帽筋に分散しやすいので、さらに上腕二頭筋にまで分散しないようオフサムグリップを推奨します。
動画も参考にしてみてください!
前傾する方法についても解説されています。
一般的なサイドレイズが効きにくい理由
基本中の基本の種目として最初に紹介しましたが、実は解剖学的に見ると効きにくい種目なのです。
その一番の理由が肩関節の外転動作の可動域が非常に狭いという点にあります。
実際には45~60°くらいまでが肩関節単体の動作で、そこから先は肩甲骨が動き始めるため僧帽筋が関与してしまうのです。
ダンベルの負荷は真下にかかるので、立った姿勢で動作方向と負荷方法が真逆になるのは水平位。
つまりどうしても僧帽筋の関与を受けやすいという問題点を抱えています。
そのためにこれから紹介するようなバリエーションが効果的になるのです。
インクラインサイドレイズ
インクラインサイドレイズは最近トレーニーに大人気で今や定番になりつつあるトレーニング種目です。
角度をつけることによって、直立のサイドレイズでムダにしていた可動域のロスをカットできます。
【準備】
① インクラインベンチを40~60°程度にセットする
② 横に腰掛けてダンベルを片手に持つ(フルカン、オフサムフィンガー)
【動作】
③ 身体の真横ではなく前側から裏拳をするイメージで挙げていく
④ 水平よりやや高めまで挙げたら1~2秒キープする
⑤ ゆっくりと下ろしていき、負荷が抜ける前に動作を切り返す
⑥ 繰り返し
インクラインサイドレイズはストレッチ種目?
身体の正面までダンベルを下ろしても重力がかかり、負荷抜けしにくいのがメリットと言えます。
とは言えダンベルの負荷と動作の方向が釣り合うのは水平位で、これは肩関節の外転動作の中~終動位です。
肩甲骨が動作する範囲まで及ばないので、僧帽筋の関与を抑えやすいメリットはあります。
一方で脇が閉じたストレッチポジションでも確かに負荷はかかりますが、その大きさはさほど大きくはありません。
つまり一般的にはストレッチ種目と位置付けられてますが、その効果をメインで狙えるほどではないってことです。
肩甲骨(僧帽筋)の動作範囲を避けて三角筋中部のみだけに集中できるコントラクト~ミッドレンジ種目という位置づけが正確でしょう。
インクラインサイドレイズの注意点
この種目の注意点は身体とベンチの背面の垂直を維持し続けること。
ダンベルの動きに身体がついて行ってベンチ上でゴロゴロしてしまうと、体幹の反動でダンベルを挙げてしまいます。
「動くのは腕だけ」という意識を持ち続け、無理な重量を扱わないようにしましょう。

普通のサイドレイズより重量は軽くなるはずだよ、
動画も参考になるので観てみてください。
スキャプラプレーンサイドレイズ
スキャプラプレーンサイドレイズは最近、インクラインサイドレイズに代わって人気になりつつある種目です。
狙いは1つ前のインクラインサイドレイズと近いですが、一応別の種目として紹介します。
【準備】
① ベンチの背を45~60°に設定する
② ダンベルを両手に持ち、ベンチに背を当てて腰掛ける
【動作】
③ 体側から30°程度正面寄りの角度でダンベルを挙上する
④ 水平まで挙上し、負荷が抜ける直前まで下ろす
⑤ 繰り返し
角度をつけることで肩関節の可動域の範囲内だけで動作する点はインクラインサイドレイズと同様。
インクラインサイドレイズとの大きな違いは、両手を同時に動作できる点と肩甲骨の動作を徹底的に抑えられる点です。
ベンチの背で肩甲骨を物理的に固定すると同時に、肩甲骨の面に沿った角度で動作することで僧帽筋の関与を劇的に緩和できます。
この肩甲骨面に沿う動作角はスキャプラプレーンサイドレイズに限らず、他のサイドレイズのバリエーションでも有効なテクニックです。
インクラインベンチなどが無いトレーニング環境の場合、スタンディングで行うサイドレイズで試してみてください。
バリエーションとしてはダンベルのほか、ケーブルマシンの正面にベンチを設置して行う方法もあります。
この方法は禁止されてるジムもありますが、OKならやってみてもいいでしょう。
ライイングサイドレイズ
ここまで解説してきた種目はどれもコントラクト~ミッドレンジで有効な種目でした。
しかしこれでは筋肥大に効果的な最大出力とストレッチの刺激が足りません。
僧帽筋の関与で上手く効かせられないことが三角筋中部が発達しない主因であることは間違いありません。
しかし効果的な刺激が不足してることも三角筋中部の発達を阻んでいる大きな原因と言えます。
そこで有効な種目としてオススメするのがライイングサイドレイズという種目です。
方法は非常にシンプルで、インクラインサイドレイズをさらに極端にしたようなものになります。
① ダンベルを片手に持ち、フラットベンチ(なければ床)に体側をつけて横になる
② ダンベルを身体の前面に下ろし、体側よりやや前方に向かって挙上する
③ 繰り返し
非常にシンプルですが、身体を完全に横たえることで脇を閉じたポイントでダンベルの負荷と動作の方向が釣り合います。
発揮する筋力が強いポイントなので、高負荷でメカニカルストレスを与えるのに非常に効果的です。
さらに水平より下のポジションでも負荷が残るので、同時にストレッチ負荷も強く得られます。
床でもOKですが、ストレッチ刺激の視点ではボトムまでしっかり下ろすのが理想なのでベンチに寝る方がより効果的です。
逆にあまり高くまで挙上しても負荷が抜けるだけで、大きな効果はありません。水平よりやや高い位置から下で動作しましょう。
ケーブルサイドレイズ
ケーブルマシンの利点は最初から最後まで負荷が均等にかかることです。
もう1つのポイントが負荷のかかる方向を調節できる点にあります。
ケーブルのプーリーを低い位置に設定する方法が一般的ですが、これではマシンの利点の1つ目だけしか活かせていません。
大半の種目と同じくコントラクト~ミッドレンジ種目になってしまいます。
もちろんこれでもOKですが、ケーブルマシンの利点を最大限に発揮するならストレッチ種目として使いましょう。
【準備】
① ケーブルマシンのプーリーを手よりやや高い位置にセットする
② アタッチメントはグリップか、手首(足首)用のベルトを使用
③ 脚を肩幅に開いてマシンに横を向いて立つ
【動作】(片手ずつ行う)
④ スタートポジションは脇を閉じた姿勢よりさらに内側(身体の前を通す)
⑤ ケーブルをプーリーから引き出し、4時から8時の範囲で動作する
⑥ 繰り返し
コントラクトと同じくストレッチポジションでも無理をするとインピジメントに繋がります。
プーリーを過度に高い位置に設定すると肩を痛める可能性があるので、自分の肩の可動域と相談してください。
アップライトロウ

アップライトロウは肩の収縮を強く出来るコントラクト種目です。
ややマイナーな種目ですが、サイドレイズで脇を開く意識がしにくい人がイメージを掴む目的でも有効です。
【準備】
① 肩幅に足を開いて立ち、両手にウェイトを持つ
【動作】
② 肘を90°近くに曲げながら脇を開いていく
③ ウェイトを胸の高さまで挙げたら1~2秒キープする
④ ゆっくりと下ろしていき、負荷が抜ける前に動作を切り返す
⑤ 繰り返し
アップライトロウのバリエーション
アップライトロウはダンベル、バーベル、ケーブルマシンを使ったバリエーションがあります。
ダンベルは左右それぞれ均等に負荷をかけられるメリットがある一方で、扱える負荷は小さい点がデメリットです。
バーベルのメリットとデメリットはダンベルのものと真逆になります。
ケーブルマシンは可動域の全体でほぼ均等にかけられるメリットがありますが、アタッチメントの限界で左右を個々に刺激しにくいのが難点です。
ローイングマシンに仰向けに寝て、肩甲骨を固定して動作するという少しトリッキーな方法もあります。
海外のフィジーカーなどが取り入れてるテクニックなので、気になる人は試してみてください。
両手の幅はどれくらいがベストか?
また両手の幅については色々な意見があります。
両手の幅を狭くすると動作の可動域が広くなる一方で、ケガのリスクが高くなるのが問題です。
一方で手幅を広くすると可動域は制限されますが、その分だけ無茶な動きが出来なくなるので、ケガのリスクは低減されます。
個人の筋繊維の走行方向や負荷の大きさよっても三角筋への効きが異なるので、この辺りは各自試してみるしかなさそうです。
アップライトロウの注意点
可動域を広く使うことで、インクラインサイドレイズなどよりも強く収縮させられる点がメリットです。
しかしこれは同時にケガのリスクでもあります。
肩のインピジメントの原因になりやすい種目と言われてもいるので、重量にこだわらないのが吉です。
その点ではバーベルアップで行うライトロウに利点は無いのかもしれません。

重量にこだわると前腕が力み過ぎるしね
脇を開く動作に集中し、ウェイトを挙げようと躍起にならないことはケガの防止と同時にトレーニング効果を上げることにも繋がります。
かなり軽い重量で行い、肩を温めるアップ扱いにするというのもアリです。
いずれにしても肩の外転動作の可動域の外まで動作してしまうので、違和感があれば迷わず外しましょう。
また肩をすくめる動作をしやすく、僧帽筋に分散しやすいのでその点も要注意!
まとめ
広い肩幅を作る上で欠かせない三角筋の中部のトレーニング種目について解説しました。
肩の広さは当然のこととして、メリハリのある腕を作るためにも中部は必須のパーツです。
鍛えている人はかなり多いですが、同時になかなか効果が上がらない人が多い部位でもあります。
その理由は主に肩甲骨が動作し、僧帽筋に負荷が分散してしまう点です。
もう1つ見落とされがちな理由が、ミドルデルタの筋トレ種目のほとんどがコントラクト種目ってこと。
これでは筋肥大に有効な3つの刺激のうちの1つしか与えることが出来ません。
そこでオススメしたいのが、横になって行うサイドレイズとケーブルマシンのプーリー位置を工夫したサイドレイズです。
また三角筋は「この軌道が正解」という共通の答えはありません。
自分の筋肉の走行方向に沿うように動作する必要があるので、観察と研究は必須です。
種目のバリエーションや負荷よりも、ちゃんと効かせられているかを今一度チェックしてみてください。
効果的に鍛えて憧れのメロン肩を作り上げましょう!てなとこで。
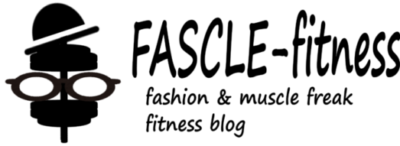



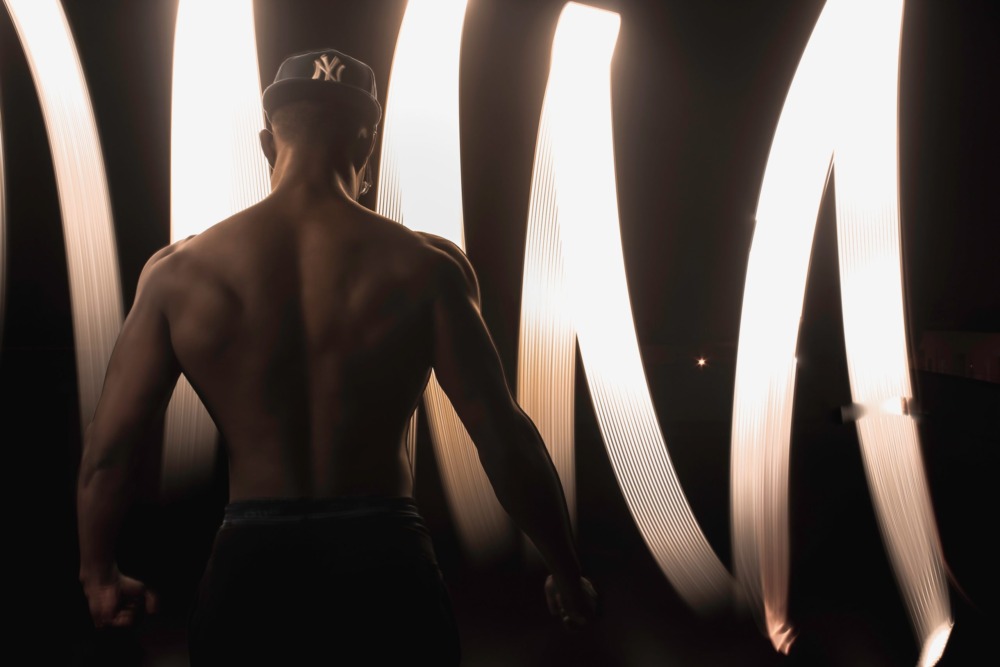









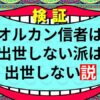
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません